レッスンスケジュール
週1で1年で57回ぐらいのレッスンじゃ才能がある人以外はこんな感じかもしれない
タンゴは始める
1年目:基本ステップを覚える
2年目:基本リードを少し覚える
3年目:ステップとリードが融合しはじめる
4年目:リードオンリー
5年目:ミュージカリティー
レッスンする理由は、これだと思う
踊りを覚えるとは別に、レッスンする理由は
お互いの身体に負担のかからない踊り方を習得すること
相手のカラダに負担を掛けるようにすること
無理な負担が掛かれば、カラダも壊れるし、そういう人とは踊りたくないになる
たとえば
自分で立てずに、相手に寄りかかっている
腕が突っ張ってすごく力がかかっている
ミロンガで、断られたり、誘われなくなったりするのであれば
ここらんも一度見直したりするといいかもしれない
他のダンスとの違い
タンゴでは腰はひねらない
ある意味、他のダンスと大きく違うところだと思う
これは最初に言ってあげるべきこと
無茶なカラダの動きは要求しない
ダンスはカラダに無茶させるイメージがあるが
ミロンガのダンスなら、自然体で動けるダンスにするのがベスト
無理な姿勢や、全身に力が入っているとかは、不自然
大げさはかっこ悪し、不自然
決して、タンゴは、カラダを無理に動かすことは一切ない
自然体のまま踊りにしていくもの
タンゴは、リードとフォローというペアダンスになる
タンゴは、リードとフォローという
それぞれに役割があって踊る
リーダする人をリーダと呼び、フォローする人をフォロワーと呼ぶ
リードする側は、音楽を聞いて、どんな踊りをするのかを考えて、それを相手に伝える人
フォローする側は、リーダからの指示をキャッチして、その流れにそって踊る人
一般には、リーダは男性、フォローは女性になる
タンゴのレッスンは、それぞれが、その役割を学ぶことになる
カミナンド
カミナンドは、二人で一緒に歩くことだけど
普通に歩くのとはちょっと違う
さらに、かっこよくキレイに見せるためには
そのためのカラダ作りにも励まなければならない
骨盤を立てるとか、骨盤から動かしていくとか
ぶれない軸を作るとか
つま先から着地するとか、逆に踵から着地するとか
小指で床を探るように歩くとか
溜めを作るとか、ダブルテンポで小刻みに動くとか
下に踏む力を強くしたり、弱くしたりとか
いろいろ練習を積まなければならない
この一連の動作は、タンゴの基本でありながら、永遠の課題と言われている
アブラッソ
タンゴには、アブラッソという、2人が組む姿勢がある
タンゴの中で一番具体的に教えられないものかもしれない
にもかかわらず、一番のコアだったりするので厄介
アブラッソも永遠の課題
タンゴスタイルの違い
最初から、いろいろなタンゴスタイルを知っていて、選んで始めることは稀
どの環境でタンゴを始めるかで決まってしまう
また、あとから、スタイルを変えることは、カラダが覚えてしまうと難しいと思われる
Urquiza Tango(ウルキサスタイル)
ブエノスアイレスの郊外ウルキサ地区(スンデルランド)で踊られるタンゴ
クローズで、少し前傾で、左ずれのアブラッソのスタイル
リーダーが右側でリードするタイプ
少し左にずれることで腕がフリーになるし、頭の位置もずれてるので楽
かなり機動性が高い
一般に一番多いタイプの組み方
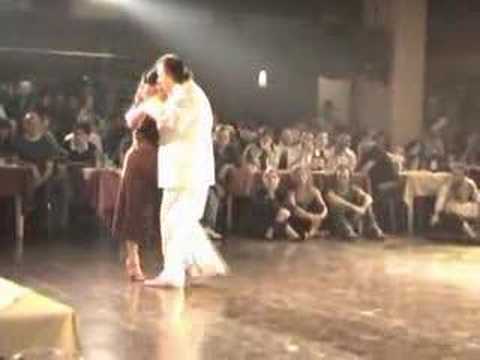
セントロスタイル
ブエノスアイレスのセントロ地区で踊られるタンゴ
都会っ子な、おじいちゃんたちがこの踊りをしている
真正面に構えて、アブラッソは深い
胸リードだけで踊る感じ
胸を付けるためにどうしても前傾にならざるを得ない
が、前傾姿勢は人それぞれ
コンタクトポイントが多い
ステップは小さくしか動けない
サロンタンゴ(Salon Tango)
アルゼンチンタンゴは、サロンタンゴとも言われる
日本では、大会用のタンゴの一般名称になっている
ダンスとしての王道
また、大会で、いい戦績を残すことが
その人達の踊りの原点になっている
体幹鍛え、所作に注力し、動きの美を追求する
魅せるタンゴに欲望の根幹がある
ヌエボ(Nuevo Tango)
新しいタンゴのスタイル
伝統的なタンゴの曲以外でも踊るイメージ
ただし、タンゴのリードの方法論は同じ、ステップの種類が多いだけ
タンゴスタイルの違いによりタンゴも違ってくる
タンゴのスタイルにより、タンゴの組み方が変わり、組み方により動きが制約されることになる
リードの仕方やカラダの使い方も違ってくる
それにより、コネクションの使い方も違ってくる
違ってくるという表現は、もちろん共通部分もある
だから、タンゴのスタイルが違っても、踊れる
ただ、ここらへんが頭の中で整理されて
どんなタンゴスタイルでも踊れるようになるには、やはり時間が掛かる
もっと先生について議論すべき
先生によって、考え方や教え方が違う
そもそもステップのカタチしか教えないは論外
タンゴは普通のダンスとは違うと思うので
だからこそ、もっと先生について議論すべきだと思っている
たとえば
ダンスをエンタメサービス業として先生も居れば
踊れるプロとしての先生も居れば
教えるプロも居る
古典芸能と同じ師匠というポジションで、伝統を継承する先生も居る
なにより、先生も常に進化している
いろいろな違いを把握した上で、自分に合ったところに行ければいいと思うけど
このネット情報社会でも、なかなか知ることができない
なぜ、タンゴの踊りが成立するのか?
ひたすら、なぜ、タンゴの動きが成立するのかだけを考える
なぜ、始めての人とでも、即興でタンゴが踊ることができるのか?
そのためには、何を習得しなければならないのか?
ステップのカタチより、こちらを教えてくれる先生じゃないと
自分なりのタンゴを踊るところに達するのは難しいと思う
タンゴの習う側の心構え
愛を教えることができないように
タンゴの本質を教えることはなかなかできないと思うから
全部教えてもらえるようなものではない
ということを知っておくべきだと思う
ある程度習った先は、自分で考えるしかないし
考えるためのヒントをもらうためにレッスンに行く
タンゴレッスンとは、そういうものだと思う

